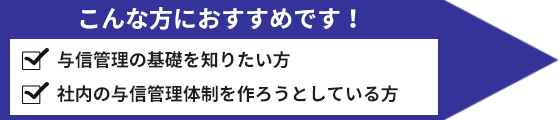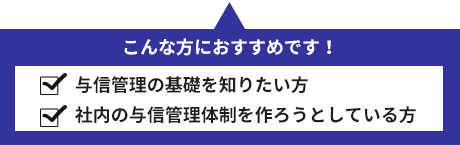2024年12月10日
追加融資拒否で粉飾に着手
企業で粉飾決算が発覚しても、事件化して経営者が逮捕されるケースは滅多にありませんが、大阪の医療機器専門商社「S社」(2023年9月民事再生手続開始決定)は今年の5月に、東京のベアリング商社「H社」(2023年7月破産手続開始決定)は6月に、それぞれ金融機関から融資金を詐取した疑いで経営者が逮捕されました。
この名門老舗企業2社の大粉飾事件の共通点としては、20年以上の長きにわたる大規模な粉飾が、コロナ後の局面でついに発覚したという点が挙げられます。
S社では遅くとも1999年頃には粉飾決算が恒常的に行われていたとされ、H社は4代目社長が就任した2003年より粉飾に着手したと言われています。H社の4代目社長が粉飾に及んだ背景としては、前任の3代目社長の時代に取引金融機関に決算内容の不芳を理由に追加融資を拒否されたことがきっかけであったようです。
粉飾で20年生き延びる
その頃の時代背景、おおよそ1990年代の後半から2000年代の前半にかけての金融環境を想起しますと、バブル経済崩壊後の金融危機下にあって、いわゆる「貸し渋り」や「貸し剥がし」が横行していた時代です。
巨額の不良債権を抱えた金融機関は、自身の自己資本比率改善による経営安定化のために、融資先の中小企業への融資を控え、場合によっては強引に融資金を引き上げるということも行われました。連鎖的な倒産も多数発生し、多くの企業が倒産の嵐に巻き込まれることになりました。
S社やH社は、赤字企業が金融機関から融資を受けられずに次々と倒産したそんな時代に、粉飾決算に手を染めました。その効果は抜群で、20年以上もの長きにわたって名門企業の体裁を保ち、生き延びることができたわけで、なんとも皮肉な話ではあります。
不正のトライアングル理論
ところで、不正のトライアングル理論というものがあります。これは、①不正を行わざるを得ない動機、②不正を行うことができる機会、③不正を正当化できる理由の3つがそろったときに、人は不正に走りやすいというものです。

その頃の企業で粉飾決算が行われた状況に当てはめると、①粉飾を行わないと倒産してしまうというのが強い動機となったはずで、②銀行や取引先の与信審査が甘く粉飾はバレないだろうというのが機会となり、③「バブル時代に、ゴルフ会員権購入や保養所建設など、さんざんけしかけて融資してきたのに、雨が降ったらとたんに傘を取り上げる銀行に、こちらが裏切っても問題ない」と正当化していたのかもしれません。
老舗企業の粉飾発覚はまだ続くのか…
これは筆者の想像の域を出ず、決めつけるわけには行きませんが、このような歴史・時代背景を考えますと、バブル崩壊後の厳しい時代に粉飾決算に手を染めて、今も発覚せずに生き延びている偽りの名門企業が、まだまだ多く隠れているとしても不思議ではありません。
今回、粉飾決算が行われる背景や長年に及ぶ粉飾決算の発覚が相次ぐ理由について、考えてみました。同じテーマでもう少し詳しい内容を、弊社公式YouTubeチャンネルで、動画配信していますので、ご興味がございましたら、ぜひ下記リンクからアクセスして、ご視聴いただければ幸いです。
(QSYH)
>>【スキマ時間で!無料で!マスターできちゃう動画シリーズ『取引先の決算書 定量分析の知識』】 第82回:粉飾決算の発見 その2:粉飾の動機・背景を考える
■ トーショーは企業の“変化”を捉える定性情報をご提供
トーショーでは、与信管理に欠かせない「定性情報」を収集・提供しています。抜群の情報収集力と長年にわたって蓄積されたデータベースから、お客様の与信管理ニーズに応じた配信形式でご提案いたします。
■ 財務分析から定性的な情報まで、トーショーの企業信用調査で情報収集を
企業信用調査もトーショーにお任せください。お客様の指定事項をカバーするオーダーメイド調査により、数多くのお客様から高い評価をいただいています。