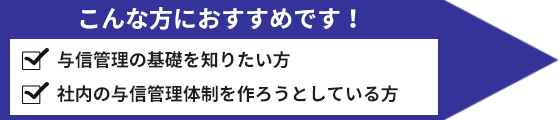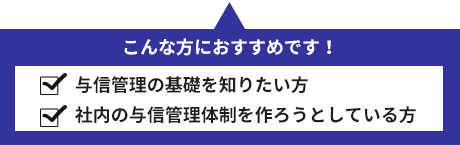2025年2月25日
決算書の見方や財務分析について記載された書籍はたくさんありますが、与信管理目線に特化して、必要な知識を丁寧に解説したものは多くありません。この【与信管理における定量分析の基本】シリーズでは、与信管理の初心者が、決算書の見方やそのために必要な最低限の会計知識を含め理解できるように、詳しく解説いたします。第11回は「財務分析 基本編(その3)」と題して、財務分析のなかでも収益性分析にフォーカスして説明します。
トーショーの公式YouTubeにて配信している【スキマ時間で!無料で!マスターできちゃう動画シリーズ『取引先の決算書 定量分析の知識』】ともリンクした内容になっておりますので、あわせてご覧いただきますと、より理解が深まります。是非ご視聴ください。
>>第33回:財務分析 基本編その6:収益性分析①
>>第34回:財務分析 基本編その7:収益性分析②
>>第35回:財務分析 基本編その8:経営状況の把握・分析
|
<目次> ■収益性分析【売上高利益率】 |
■収益性分析【売上高利益率】
売上高利益率はP/Lだけで計算
売上高利益率は、売上総利益、営業利益、経常利益、当期純利益といった、各段階の利益を分子に、売上高を分母として利益率を計算します(各利益段階の意義や捉え方は、下段「損益計算書の項目と全体イメージ」を参照してください)。
売上高利益率(%)= 各利益 ÷ 売上高 × 100
営業利益率が低い場合、その原因がP/Lの上流の粗利益(売上総利益)が乏しいためか、販売費及び一般管理費の割合が大きいためか、2通りが考えられます。その原因にフォーカスする場合には、総利益率の算出に加え、「売上高販管費比率(%) = 販売費及び一般管理費 ÷ 売上高 × 100」を算出すると良いです。
収益性分析では売上規模などの絶対額にも注目してください。また、複数期の比較で成長性分析も実施して、不自然な売上規模の急拡大がないかチェックすることも、不正取引等粉飾発見の端緒となります。
下表では、ほとんどの業種で営業利益率より経常利益率のほうが高くなっています。かつての常識は非常識ですね。
| 全産業 | 建設業 | 製造業 | 情報通信業 | 運輸業, 郵便業 |
卸売業 | 小売業 | 不動産業,物品賃貸業 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 宿泊業,飲食サービス業 | 生活関連サービス業,娯楽業 | サービス業(他に分類されないもの) | |
| 売上高総利益率 | 25.4% |
23.1% | 20.3% | 47.6% | 23.3% | 15.1% | 30.3% | 45.2% | 49.4% | 63.8% | 37.9% | 41.2% |
| 売上高営業利益率 | 3.2% | 3.9% | 3.8% | 5.4% | 0.7% | 2.1% | 1.3% | 11.2% | 6.9% | -3.9% | 0.6% | 3.3% |
| 売上高経常利益率 | 4.3% | 5.2% | 5.1% | 6.5% | 1.9% | 2.7% | 2.6% | 10.9% | 9.5% | 1.3% | 2.8% | 4.3% |
| 売上高純利益率 | 2.8% | 4.0% | 3.0% | 3.7% | 1.6% | 1.7% | 1.4% | 8.7% | 6.5% | -0.1% | -1.4% | 2.9% |
※『中小企業実態基本調査令和5年確報(令和4年度決算実績)』のデータから計算
※ 数値は法人企業計を利用(個人企業を除く)
損益計算書の項目と全体イメージ(復習)
以前にP/Lの解説回(第5回)で示した表です。各利益が持つ意味について、再確認してください。
| 売上高 | + | 商品・製品・サービスの提供など、本業で得た収益。企業の営業規模を見る一つの目安となる。 |
| 売上原価 | - | 商品仕入あるいは製品製造にかかった費用。売上に対応した費用のみが売上原価となるため、売上原価は「期首商品(or製品)棚卸高+当期商品仕入高(or当期製造原価)-期末商品(or製品)棚卸高」で算出される。 |
| 売上総利益 | = | 粗利、粗利益とも。商品・製品等の付加価値が高く、高価格で販売できていれば総利益率が高くなり、逆に価格競争に巻き込まれているような場合は低下する。その会社の技術力、商品力などが反映される。ここが赤字ということは原価割れで商売をしているということ。 |
| 販売費及び一般管理費 | - | 販売費:販売活動にかかる費用。一般管理費:会社運営にかかる費用。人件費、家賃、広告費、交通費、光熱費など様々。減価償却費は実際にはキャッシュアウトがない費用であることに留意。 |
| 営業利益 | = | 本業のもうけ。営業活動によってもたらされる利益。これが毎期赤字の会社は、継続性が危ぶまれる。 |
| 営業外収益 | + | 主なものは受取利息や受取配当金。その他は、受取家賃、雑収入など。 |
| 営業外費用 | - | 主なものは支払利息。その他は、有価証券売却損、雑損失など。 |
| 経常利益 | = | 企業の総合的な実力を示すものとして日本では伝統的に重視する人が多い。近年は低金利の影響もあり、営業外収益が営業外費用を上回る傾向が多く、営業利益よりも経常段階の利益が大きくなる逆転現象が見られる。 |
| 特別利益 | + | 所有する土地・建物や長期保有の有価証券売却など臨時的・例外的に発生した利益のこと。 |
| 特別損失 | - | 巨額の貸倒損失、災害損失など臨時的・例外的に発生した損失のこと。 |
| 税引前当期純利益 | = | 法人税等を払う前の利益。 |
| 法人税等 | - | 法人税、住民税、事業税の法人3税。 |
| 当期純利益 | = | 純利益、最終利益とも言う。マイナスの場合は純損失。純資産を増やす源泉 |
■収益性分析【資本利益率】
資本利益率はB/SとP/Lの合わせ技
資本利益率は、B/Sの総資産や自己資本などを分母に、P/Lの営業利益や経常利益などを分子として計算します。最もポピュラーなものは、総資本経常利益率(ROA)と自己資本利益率(ROE)です。分母は前期末と当期末の平均値を採用するべきですが、回転率の計算と同様実務上は期末数値を用いていることが多いです。
総資本経常利益率(%) = 経常利益 ÷ 総資本 × 100
自己資本利益率(%) = 当期純利益 ÷ 自己資本 × 100
自己資本利益率は株式投資の世界では重視されますが、与信管理の世界ではあまり重視しません。なぜなら、自己資本利益率は、安全性を犠牲にして分母の自己資本を小さくすることでも数値が良くなるためです。
資本利益率は、売上高利益率と資本回転率に分解できます。資本利益率は、収益性と効率性の分析を含む、総合分析指標という側面があります。特に総資本経常利益率は、会社全体の資産を分母に、総合的な収益性を示す経常利益を分子としていますので、まさに企業の総合力を示す代表的な財務指標と言えるでしょう。
総資本経常利益率の分解 = (経常利益 ÷ 売上高) × (売上高 ÷ 総資本)
総資本経常利益率の分解 = 売上高経常利益率 × 総資本回転率
余談ですが、ROA(Return On Asset)といった場合、総資本経常利益率を指す場合が多いと思いますが、その他の組み合わせとしては、経営資本営業利益率、総資本事業利益率なども見かけます。それぞれの資料でどのような算式が使われているか確認すると良いでしょう。
経営資本 = 本業で稼働している資産のみ
※ 経営資本の計算例 = 総資産 - 建設仮勘定 - 投資その他の資産 - 繰延資産
事業利益 = 金融費用を含まない利益
※ 事業利益の計算例 = 営業利益 + 受取利息・配当金 等
収益性と効率性のトレードオフ
前の項目で、総資本経常利益率は、売上高経常利益率と総資本回転率に分解できることを示しました。下表では、総資本経常利益率の業界平均の下に、売上高経常利益率と総資本回転率も併記してみました。
総資本経常利益率については、全業種でそれほど大きな差はないことがわかると思います。一方で、売上高経常利益率や総資本回転率には業種ごとに大きな差があると思います。このことが示すのは、収益性と効率性は「あちらを立てれば、こちらが立たず」のトレードオフの関係にあるということです。
例えば、製造業では売上高経常利益は5%を超えていますが、卸売業では3%に届きません。一方、製造業の資本回転率は年0.96回転ですが、卸売業は年1.70回転と大きく上回っています。つまり、販売業のような利益率が低い業態の会社が生きていくためには回転率を上げる必要があり、逆に製造業など大きな資本投下が必要で回転率の低い会社は利益率が高くなければ立ち行かないということです。利益率が低い業態で、回転率が悪化するような場合にはよくよく注意しなければなりません。
| 全産業 | 建設業 | 製造業 | 情報通信業 | 運輸業, 郵便業 |
卸売業 | 小売業 | 不動産業,物品賃貸業 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 宿泊業,飲食サービス業 | 生活関連サービス業,娯楽業 | サービス業(他に分類されないもの) | |
| 総資本経常利益率 | 4.27% | 5.61% | 4.86% | 6.72% | 2.05% | 4.55% | 4.28% | 3.06% | 6.27% | 1.20% | 2.48% | 5.07% |
| 売上高経常利益率 | 4.3% | 5.2% | 5.1% | 6.5% | 1.9% | 2.7% | 2.6% | 10.9% | 9.5% | 1.3% | 2.8% | 4.3% |
| 総資本回転率 | 1.00回 | 1.09回 | 0.96回 | 1.03回 | 1.09回 | 1.70回 | 1.68回 | 0.28回 | 0.66回 | 0.96回 | 0.90回 | 1.19回 |
| 自己資本利益率 | 6.6% | 9.2% | 6.2% | 6.9% | 5.0% | 6.7% | 6.7% | 6.8% | 8.2% | -0.7% | -3.6% | 7.4% |
※『中小企業実態基本調査令和5年確報(令和4年度決算実績)』のデータから計算
※ 数値は法人企業計を利用(個人企業を除く)
※自己資本は「純資産」で計算
■YouTubeでも詳しく解説!
本ページの内容は、トーショーの公式YouTubeにて配信している【スキマ時間で!無料で!マスターできちゃう動画シリーズ『取引先の決算書 定量分析の知識』】ともリンクした内容になっております。下記リンクのとおり、第33回~第34回が本ページの内容に沿った内容となっております。復習としてもご活用いただけますので、是非ご視聴ください。
また、YouTubeでしか説明していない内容の第35回もあります。第35回では、一連の財務分析基本編シリーズの仕上げとして、財務データの実例を用いて実際に主要な財務指標を計算し、経営状況をいかに把握するか、実践的な解説をしています。数値データだけでなく、その会社がおかれている状況も示し、定量面と定性面から総合的な分析を試みています。是非、こちらもあわせてご視聴ください。
 >>【スキマ時間で!無料で!マスターできちゃう動画シリーズ『取引先の決算書 定量分析の知識』】第33回:財務分析 基本編その6:収益性分析①
>>【スキマ時間で!無料で!マスターできちゃう動画シリーズ『取引先の決算書 定量分析の知識』】第33回:財務分析 基本編その6:収益性分析①
 >>【スキマ時間で!無料で!マスターできちゃう動画シリーズ『取引先の決算書 定量分析の知識』】第34回:財務分析 基本編その7:収益性分析②
>>【スキマ時間で!無料で!マスターできちゃう動画シリーズ『取引先の決算書 定量分析の知識』】第34回:財務分析 基本編その7:収益性分析②
 >>【スキマ時間で!無料で!マスターできちゃう動画シリーズ『取引先の決算書 定量分析の知識』】第35回:財務分析 基本編その8:経営状況の把握・分析
>>【スキマ時間で!無料で!マスターできちゃう動画シリーズ『取引先の決算書 定量分析の知識』】第35回:財務分析 基本編その8:経営状況の把握・分析
■トーショーは企業の“変化”を捉える定性情報をご提供
トーショーでは、与信管理に欠かせない「定性情報」を収集・提供しています。抜群の情報収集力と長年にわたって蓄積されたデータベースから、お客様の与信管理ニーズに応じた配信形式でご提案いたします。
> 企業信用情報のサービス紹介はこちら
> 資料ダウンロード・資料請求はこちら
■財務分析から定性的な情報まで、トーショーの企業信用調査で情報収集を
企業信用調査もトーショーにお任せください。お客様の指定事項をカバーするオーダーメイド調査により、数多くのお客様から高い評価をいただいています。